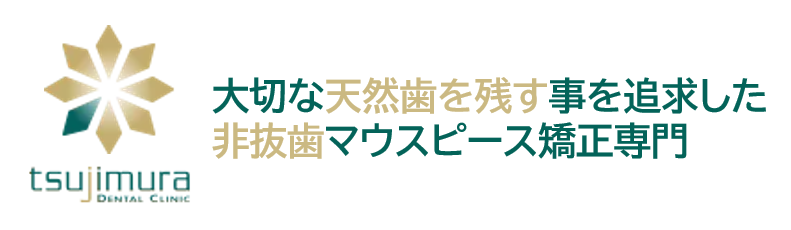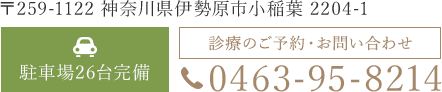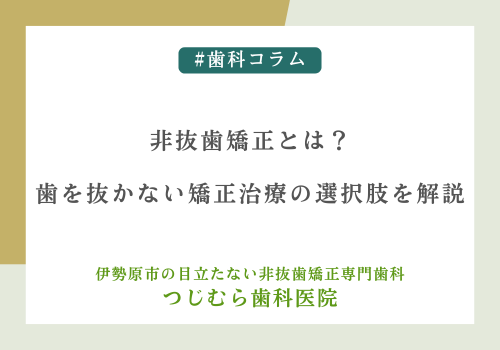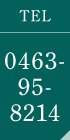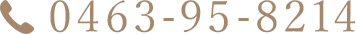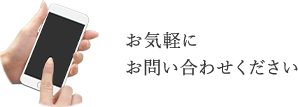なぜ「歯を抜かない矯正」が注目されているのか?

「できるだけ歯を抜きたくない」——そう感じる患者様は年々増えています。矯正治療において「歯を抜く」ことは、従来の一般的な方法として多く採用されてきましたが、近年では「非抜歯矯正(歯を抜かない矯正歯科)治療」が注目されるようになっています。その背景には、治療技術の進化や、患者様の健康志向の高まりがあります。
抜歯矯正との違いとは?
従来の矯正治療では、歯並びを整えるスペースを確保するために、4本の小臼歯(前から数えて4番目と5番目の歯)を抜くことが一般的でした。これにより、歯を後方に移動させることで、見た目の美しさや噛み合わせの改善が行われてきました。しかし、抜歯によるスペース確保は、歯列全体にかかる力のバランスに影響することもあり、慎重な診断と治療計画が求められます。
一方、非抜歯矯正は、できる限り歯を残したまま、歯列を広げたり、歯の位置を工夫したりしてスペースを作り出す治療法です。装置や技術の進歩により、歯を抜かずに矯正を行えるケースが増えており、これが患者様にとって大きな魅力となっています。
非抜歯矯正が選ばれる理由
非抜歯矯正が注目される理由の一つに、「自分の歯を残したい」という患者様の希望があります。永久歯は、一度失うと二度と生えてきません。そのため、できるだけ歯を抜かずに機能的かつ美しい歯並びを実現したいというニーズが高まっています。
また、非抜歯矯正は、歯を抜くことで起こり得る副作用やダウンタイムが少ないことも利点です。抜歯後の痛みや腫れ、さらには噛み合わせやフェイスラインへの影響を心配される方にとって、非抜歯矯正は安心感のある治療選択肢と言えるでしょう。
患者様の負担を軽減する治療法
非抜歯矯正は、物理的・精神的な負担を減らすという点でも優れています。抜歯に対する不安感を抱く方は少なくありません。また、抜歯後の治癒期間を必要としないため、治療開始までのスピードが早いという特徴もあります。
さらに、歯を抜かないことで噛み合わせや顔の輪郭が極端に変化しづらく、より自然な仕上がりが期待できる点も、患者様の満足度を高めています。もちろん、すべての症例で非抜歯矯正が適しているわけではありませんが、適応できるケースであれば、そのメリットは非常に大きいといえます。
非抜歯矯正のメリットとは?
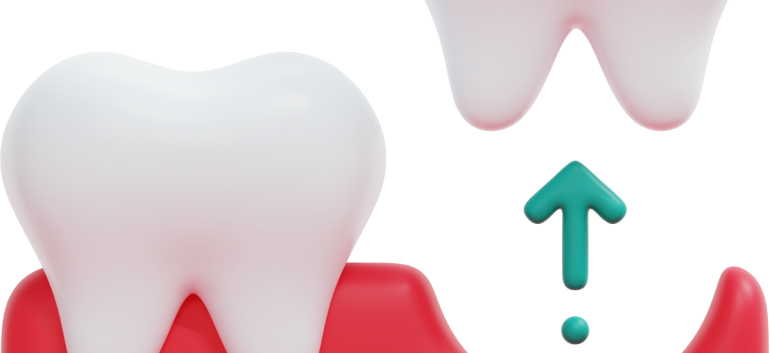
非抜歯矯正(歯を抜かない矯正歯科治療)は、ただ単に「歯を抜かない」というだけではなく、患者様の健康や見た目、将来の生活にさまざまなメリットをもたらします。矯正治療を検討する上で「抜歯あり」「抜歯なし」の選択肢がある場合、なぜ非抜歯矯正が選ばれることが多いのか。その理由を3つの観点からご紹介いたします。
自然な歯並びを保てる
人間の歯は、本来の生え方や噛み合わせに意味があります。非抜歯矯正では、歯列のアーチ(歯の並びの曲線)を崩さず、自然な形を活かしながら歯並びを整えることができます。歯を抜くことで生まれるスペースを使わず、顎の発育や歯列の幅をうまく調整して整えていくため、仕上がりが自然で、無理のない歯並びを実現しやすいのが特長です。
また、歯列全体のバランスを整えることにより、口元の印象がやわらかくなる傾向もあります。矯正後に「笑ったときの口元が自然になった」「口を閉じやすくなった」といった変化を感じる方も多くいらっしゃいます。
顎のバランスを整え、顔立ちが美しくなる
歯並びは顔全体の印象に大きな影響を与えます。特に、上下の顎のバランスや噛み合わせの位置は、横顔やフェイスラインに直結します。非抜歯矯正では、顎の骨格や筋肉の成長を促すような方法を採用することもあり、単なる「見た目の矯正」にとどまらず、骨格的なバランスを整えることが可能です。
特に成長期のお子様や、顎が小さめな方には、顎の発育をサポートする治療を組み合わせることで、より整った顔貌へと導くことが期待されます。また、大人の方でも、抜歯によって起こる可能性のある「ほうれい線の強調」や「頬のこけ」などを避けたい場合には、非抜歯矯正が有効な選択肢となります。
抜歯リスクの回避による健康への配慮
歯を抜くという処置には、外科的なリスクやダメージが伴います。抜歯後の腫れや痛み、感染症のリスク、さらには歯の本数が減ることによる噛み合わせの変化などが懸念されます。特に健康な永久歯を抜くことに抵抗を感じる方は多く、非抜歯で矯正ができるのであれば、それに越したことはありません。
また、歯を残すことで噛む力のバランスが保たれ、将来的な歯の寿命にも良い影響を与えると考えられています。歯は1本1本に役割があり、それぞれの歯がバランスよく機能することで、お口全体の健康が維持されるのです。
非抜歯矯正の適応条件

「できれば歯を抜かずに矯正したい」——これは多くの患者様が抱く願いです。しかし、すべての方に非抜歯矯正が適応できるわけではありません。歯や顎の状態、噛み合わせの特徴などを総合的に判断し、専門的な診断のもとで治療方針が決定されます。ここでは、非抜歯矯正が適しているケースや、年齢・症状ごとの対応についてご紹介します。
どんな人に向いているのか?
非抜歯矯正が可能なケースとして多いのは、以下のような特徴を持つ方です。
・顎の大きさと歯のサイズのバランスが取れている方
・歯並びの乱れ(叢生)が比較的軽度な方
・上下の前歯が前方に突出しておらず、骨格的なズレが小さい方
・すでに親知らずを抜歯済みで、奥歯の移動が見込める方
これらの条件を満たしていると、歯を抜かずにスペースを作ることで自然な歯列に整えることが可能です。歯列のアーチを広げたり、歯の角度を微調整したりすることで、きれいな噛み合わせに導きます。
年齢制限はあるのか?
非抜歯矯正は、成長期の子どもから成人まで幅広い年齢層で対応可能ですが、それぞれの年齢によってアプローチが異なります。
子どもの場合
成長期のお子様は、顎の骨がまだ柔らかく、成長をコントロールしながら矯正治療を進めることができます。顎の幅を広げたり、前方へ誘導したりすることで歯が並ぶスペースを確保しやすく、非抜歯での治療が成功しやすい傾向にあります。
大人の場合
成人でも非抜歯矯正が可能なケースは多くあります。特に近年は、マウスピース型矯正装置などによる歯列拡大の精度が上がっているため、抜歯せずに治療できる選択肢が増えています。ただし、骨の柔軟性が子どもに比べて低いため、無理な移動は避ける必要があり、治療計画の立案がより重要になります。
歯並びの状態による治療の可否
非抜歯矯正が難しいとされるのは、以下のようなケースです。
・歯の大きさに対して顎の骨が極端に小さい場合
・上下の顎に大きな前後差(出っ歯・受け口)がある場合
・歯が重なり合っている(叢生)が高度な場合
・噛み合わせが深すぎる「過蓋咬合」や開きすぎる「開咬」のケース
このような場合でも、先進の矯正技術や補助的な治療(顎の拡大装置など)を組み合わせることで、非抜歯での治療が可能となることもあります。大切なのは、安易に抜歯ありきで考えるのではなく、「抜歯しなくても良い可能性」を専門医と一緒にしっかり検討することです。
あなたのお口の状態は非抜歯矯正の適応かも?まずはカウンセリングでチェックしましょう
治療の流れと期間

非抜歯矯正(歯を抜かない矯正歯科)治療を検討する際、「治療の全体像を知りたい」という方は多くいらっしゃいます。歯を抜かずに歯並びを整えるには、緻密な診断と計画が欠かせません。ここでは、初診から治療完了までの流れと、おおよその治療期間、そして治療中に気をつけておくべきポイントについて詳しくご紹介します。
初診から治療完了までのステップ
1.カウンセリング(初診相談)
患者様の歯並びやお悩みを詳しくお伺いします。「できれば歯を抜きたくない」「目立たない装置で治療したい」などのご希望を確認し、非抜歯矯正が可能かどうかの大まかな判断を行います。
2.精密検査・診断
レントゲン撮影(パノラマ・セファロ)、歯型採取、口腔内・顔貌写真撮影などを行い、噛み合わせや歯列の状態を多角的に分析します。顎の大きさや歯の大きさ、骨格のバランスなどを評価し、非抜歯での治療が安全かつ効果的に行えるかを診断します。
3.治療計画のご説明
検査結果をもとに、治療方法・期間・費用の目安を詳しくご説明します。使用する装置や治療の選択肢(マウスピース矯正・ワイヤー矯正など)、リスクや限界についても丁寧にご案内します。
4.治療開始(矯正装置の装着)
歯を動かすための装置を装着し、定期的に通院しながら段階的に矯正を進めていきます。歯の動き方には個人差があるため、進行状況を確認しながら調整を行っていきます。
5.保定期間(後戻り防止)
歯並びが整った後は、保定装置(リテーナー)を使って、動かした歯を安定させます。この期間は見落とされがちですが、後戻りを防ぐために非常に重要なステップです。
どれくらいの期間で歯が動くのか?
非抜歯矯正の治療期間は、患者様の年齢や歯並びの状態によって異なりますが、平均的には1年半〜2年半)程度が一般的です。軽度の不正咬合であれば1年前後で完了することもありますし、歯列全体を大きく動かす必要がある場合には3年近くかかるケースもあります。
特にマウスピース型矯正装置を使用する場合は、装着時間の遵守が治療期間に大きく影響します。1日20時間以上の装着が求められるため、患者様の協力度も治療のスピードを左右するポイントとなります。
治療中の注意点
・装置の取り扱い
マウスピースやワイヤーなど、装置の種類によって注意点が異なります。破損や紛失、食事中の扱いなどには十分注意しましょう。
・定期通院
矯正治療は、歯の動きを適切にコントロールするために、通常1ヶ月に1回程度の通院が必要です。スケジュール通りに受診することが、治療の成功には不可欠です。
・口腔内の清掃
装置が付いていることで、磨き残しやすくなる部分があります。虫歯や歯周病を防ぐためにも、丁寧なブラッシングとプロのクリーニングを併用しましょう。
非抜歯矯正に使われる装置とは?

非抜歯矯正(歯を抜かない矯正歯科治療)では、限られたスペースの中で歯を美しく整えるために、精度の高い装置や補助器具が必要不可欠です。現代の矯正治療は、患者様のニーズや生活スタイルに合わせた多様な装置が選択できるようになっています。この章では、非抜歯矯正でよく使用される代表的な装置と、それぞれの特徴や役割についてご紹介します。
マウスピース矯正(インビザラインなど)
近年、特に注目されているのがマウスピース型矯正装置です。中でも「インビザライン」は世界的に実績がある信頼性の高いシステムとして、多くのクリニックで採用されています。
マウスピース矯正は、透明な素材でできたカスタムメイドのアライナーを一定期間ごとに交換しながら、歯を少しずつ理想的な位置へと動かしていきます。見た目が目立ちにくく、取り外しができるため、食事や歯磨きのストレスが少ないのが特長です。
非抜歯矯正では、顎のアーチを広げる動きや、前歯を前方へ傾けるなどの工夫によってスペースを確保するため、歯をスムーズに動かせるインビザラインとの相性が非常に良いとされています。ただし、装着時間(1日20時間以上)を守ることが治療成功の鍵になります。
ワイヤー矯正と非抜歯の関係
ワイヤー矯正(ブラケット矯正)は、長年にわたり実績を積んできた矯正装置です。歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を接着し、ワイヤーで引っ張ることで歯を動かします。
非抜歯矯正においても、細やかな歯の動きが必要な場合や、歯列全体の調整が求められる場合には、ワイヤー矯正が有効です。近年では、目立ちにくい透明ブラケットやホワイトワイヤーの登場により、見た目の負担も軽減されています。
また、ワイヤー矯正はコントロール性能に優れているため、歯の傾きや回転の調整がしやすく、非抜歯矯正で重要な「スペースの確保と並びの微調整」にも適しています。
拡大床・急速拡大装置の役割
非抜歯矯正では、歯を抜かずに歯並びを整えるため、顎の骨を横方向に広げてスペースをつくる方法が取られることがあります。その際に使用されるのが「拡大床」や「急速拡大装置(RPE)」です。
拡大床(かくだいしょう)は、取り外し可能な装置で、主に成長期の子どもに使用されます。中央のネジを回すことで、上顎を少しずつ広げていきます。顎の発育をコントロールできる時期に使用することで、非抜歯での矯正が可能になる可能性が高まります。
急速拡大装置は固定式で、より短期間で大きな拡大が必要なケースに用いられます。成人に対しても用いることは可能ですが、骨の成熟度に応じて計画的に使用する必要があります。
これらの装置は、患者様の年齢、歯並びの状態、生活スタイルなどを総合的に判断したうえで選択されます。つじむら歯科医院では、精密な診断をもとに、患者様一人ひとりに合った装置と治療方法をご提案いたします。
矯正歯科治療の装置の種類について詳しくはこちらをご覧ください。
実際に治療された方の症例をご覧ください。
治療後のメンテナンスと後戻り対策

矯正治療は、歯並びを整えて終わりではありません。特に非抜歯矯正では、歯を抜かずにスペースを確保して動かす分、治療後の“後戻り対策”が非常に重要となります。ここでは、治療終了後にどのようなケアが必要か、そして歯並びを長く美しく保つためにできることを詳しくご紹介します。
矯正後の保定装置(リテーナー)の重要性
歯の矯正が終わると、多くの方は「これで治療が終わった!」と思われるかもしれません。しかし実際には、歯は元の位置に戻ろうとする「後戻り」の性質があり、その対策として欠かせないのがリテーナー(保定装置)です。
リテーナーは、動かした歯を現在の位置に固定し、安定させるために装着する装置です。取り外しができるタイプ(プレート型)や、歯の裏側に接着するワイヤータイプ(固定式)があります。どちらを使うかは患者様の状態によって異なりますが、リテーナーの装着を怠ると、数ヶ月で歯並びが崩れてしまうこともあるため、使用の継続が非常に大切です。
使用期間の目安は、最低でも1〜2年。その後は、就寝時のみの装着に移行することもありますが、医師の指示に従って継続使用することで、後戻りのリスクを最小限に抑えられます。
後戻りを防ぐためのセルフケア
リテーナーの使用だけでなく、日々の生活習慣やお口の使い方も後戻りに影響します。以下のようなセルフケアを心がけましょう。
・舌の位置を正しく保つ:舌が常に前歯を押すようなクセ(舌突出癖)があると、歯列が前方へ開いてしまう原因に。舌は上顎の中央に軽くつけるのが正しい位置です。
・片側だけで噛まない:左右バランスよく咀嚼することで、顎や歯列にかかる力が均等になり、歯並びの安定につながります。
・歯ぎしり・食いしばり対策:無意識のうちに歯に大きな力が加わると、歯が動いてしまうことがあります。必要に応じてマウスピースを使うなど、ナイトガードの使用を検討することも大切です。
定期検診の必要性
治療後も定期的な通院は欠かせません。歯並びのチェックに加えて、リテーナーのフィット具合、虫歯や歯周病の有無なども確認してもらうことができます。理想は3〜6ヶ月に1回程度の定期検診を受けることです。
また、後戻りの兆候が早期に発見できれば、軽微な調整で済む場合がほとんどです。少しでも違和感を感じたら、早めに相談するようにしましょう。
非抜歯矯正の成果を長く保つためには、「治療後の行動」がカギになります。歯並びが整ったあとは、美しさをキープする新たなステージの始まり。つじむら歯科医院では、矯正後のメンテナンスにも力を入れており、患者様が安心して長く笑顔で過ごせるよう、全力でサポートいたします。
非抜歯矯正の費用と保険適用の有無

矯正治療を検討する際、最も気になることの一つが「費用面」です。とくに非抜歯矯正は、精密な診断と高度な治療計画が求められるため、「費用が高くなるのでは?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。ここでは、非抜歯矯正の費用の目安、保険適用の有無、医療費控除や支払い方法についてわかりやすく解説します。
費用相場とクリニックごとの違い
矯正治療は自費診療となることが多く、費用はクリニックや治療内容によって差があります。非抜歯矯正も例外ではなく、使用する装置や治療の難易度によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
・マウスピース矯正(全体矯正):約70万〜100万円
・ワイヤー矯正(表側):約60万〜90万円
・部分矯正(前歯のみなど):約30万〜50万円
・拡大装置の使用や精密検査費用:数万円〜十数万円程度
非抜歯矯正は抜歯が不要な分、外科処置の費用がかからないことがありますが、その代わりに精密な分析や診断力、顎や歯のコントロールが求められるため、決して「安価になる」とは限りません。治療期間や使用装置、アフターフォローの内容も含め、トータルで比較検討することが大切です。
医療費控除の対象になるか?
矯正治療の費用は、一定の条件を満たせば「医療費控除」の対象になります。これは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得税の一部が還付される制度です。
矯正治療が医療費控除の対象になるかどうかは、「治療の目的」がポイントになります。
・対象になる例:噛み合わせの改善、発音・咀嚼機能の回復、顎の成長のサポートなど、医師が医学的に必要と判断した場合。
・対象にならない例:見た目のみを目的とした美容矯正(審美目的)など。
つじむら歯科医院では、医療費控除の対象かどうかも含めて、治療開始前に丁寧にご説明しております。必要に応じて、診断書の発行なども対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
分割払い・ローンの利用について
「一括での支払いが難しい」という方には、デンタルローンや分割払いに対応しているクリニックも増えています。つじむら歯科医院でも、患者様のご希望やライフスタイルに合わせた支払い方法をご提案しています。
・月々1〜3万円台からスタート可能なプラン
・クレジットカード払い対応
・医療ローン(提携金融機関)のご案内
こうした制度を活用することで、無理なく矯正治療を始められる環境が整いつつあります。
矯正治療は、見た目の美しさだけでなく、将来の歯の健康や咀嚼機能に直結する“一生ものの投資”です。価格だけで判断するのではなく、治療内容、サポート体制、医師の専門性なども含めて、信頼できる歯科医院を選ぶことが大切です。
無理のない費用プランで、理想の歯並びへ
非抜歯矯正を成功させるために大切なこと

非抜歯矯正(歯を抜かない矯正歯科治療)は、見た目の自然さや健康面への配慮から、非常に魅力的な治療法として選ばれる方が増えています。しかし、どんなに優れた治療法でも、確実な成果を出すには「正しい準備」と「信頼できるクリニック選び」が欠かせません。ここでは、非抜歯矯正を成功させるために大切な3つのポイントをご紹介します。
クリニック選びのポイント
非抜歯矯正は、限られたスペースの中で歯を美しく並べる高度な技術が求められる治療法です。そのため、歯列や顎骨の構造を精密に診断できる設備と、豊富な症例経験を持つ歯科医師が在籍していることがとても重要です。
クリニック選びの際は、以下のような点に注目するとよいでしょう。
・精密検査(セファログラムなど)の導入
・非抜歯矯正の症例数が豊富
・説明が丁寧で、無理に治療を勧めてこない
・カウンセリングでリスクや選択肢をしっかり提示してくれる
特に、非抜歯矯正に力を入れている医院では「まず抜かない選択を考える」という方針を取っていることが多く、患者様の歯を大切に扱う姿勢が感じられるはずです。
医師の技術力と実績を確認する方法
非抜歯矯正は、全体の咬合バランスや顔貌との調和を重視した設計が求められます。そのため、矯正専門医または矯正治療に習熟した歯科医師の診断と技術が結果を大きく左右します。
以下のような点を確認することで、技術力や実績の判断材料となります。
・歯列矯正学会・矯正専門資格の有無
・過去の治療症例(※ガイドラインに沿って客観的に掲載されているか)
・担当医が在籍している日数・頻度(常勤か非常勤か)
・治療後のフォロー体制(リテーナー管理・後戻り防止の取り組み)
また、実績のある医院では「なぜ非抜歯矯正が可能か」という理由を、画像や模型を使って丁寧に説明してくれることが多く、納得感を持って治療を始めることができます。
自分に合った治療法を見つけるコツ
「非抜歯矯正がいい」と聞くと、無理にそれを選びたくなる方もいらっしゃいます。しかし、どんなに良い治療法であっても、自分の口腔内に合っていなければ意味がありません。矯正治療は「オーダーメイドの医療」であり、自分の歯並び・顎・ライフスタイルに合わせて治療法を選ぶことが成功のカギです。
たとえば、
・通院頻度を減らしたい方 → マウスピース矯正
・微細なコントロールが必要な歯列 → ワイヤー矯正
・顎の発育を促進したいお子様 → 拡大装置や早期治療
など、それぞれに適した装置や方法があります。
まずは「自分の状態を正しく知ること」、そして「納得できる治療計画を立てること」が、満足のいく結果へとつながります。
非抜歯矯正で期待できる変化と治療目標

「歯を抜かずに、どこまで歯並びがきれいになるのか?」
非抜歯矯正を検討される多くの患者様が気になるポイントのひとつです。非抜歯矯正は、審美的な変化だけでなく、咬み合わせや顔貌の調和、日常生活の快適さといった“機能面”でもさまざまな改善が期待できる治療法です。この章では、非抜歯矯正がもたらす主な変化や治療目標について、医学的根拠に基づいてご紹介します。
非抜歯矯正で目指す歯並びのバランスとは
非抜歯矯正の治療目標は、「自然で無理のない歯列の形成」と「健康的な咬み合わせの確立」です。歯を抜かない分、顎のアーチ(歯列のカーブ)を広げたり、歯の傾きを調整したりして、限られたスペースをうまく活用しながら歯を並べていきます。
このとき重要なのは、「見た目の美しさ」と「機能的な安定性」のバランスを取ること。歯が一列に揃っていても、咬み合わせが悪ければ咀嚼や発音に問題が生じますし、逆に機能ばかりを優先して見た目が損なわれては満足度が下がってしまいます。
非抜歯矯正では、歯列全体を緩やかに広げ、自然なカーブを持った歯並びを目指すことで、見た目も機能も両立することを目的とします。
顎や顔貌への影響についての基礎知識
矯正治療は、歯だけでなく顔全体の印象にも関わってきます。とくに非抜歯矯正は、顎の骨の幅や高さを保ちつつ、歯を並べていくため、顔貌のバランスを大きく崩さずに治療を行うことができます。
たとえば抜歯矯正では、前歯を大きく後退させることで口元が平坦になる(口元の“しぼみ”)傾向がありますが、非抜歯矯正では、自然な厚みを保ちやすく、「優しい口元」「若々しい印象」を維持しやすいのが特徴です。
また、上顎・下顎のバランスや、笑ったときに見える歯のライン(スマイルライン)にも配慮することで、顔全体が調和の取れた印象になります。
治療により改善が期待できる主な口腔内の問題
非抜歯矯正で対応できる歯並びの乱れには、以下のような例があります。
・軽〜中等度の叢生(歯が重なって生えている状態)
・前歯の軽度な出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)
・上下の歯のかみ合わせが浅い過蓋咬合や、開きすぎている開咬
・歯と歯の間にすき間がある空隙歯列(すきっ歯)
これらの症状は、非抜歯矯正によって顎の幅や歯の角度を調整することで改善が見込める場合が多くあります。ただし、重度の場合や骨格に大きなズレがある場合は、抜歯や外科的処置が必要になるケースもありますので、まずは精密な診断が重要です。
治療後の生活への影響(食事・発音・清掃性など)
歯並びが整うことで、生活のさまざまな場面で変化を実感される方が多くいらっしゃいます。
・食事がしやすくなる:噛み合わせが整うことで、しっかりと食べ物を噛み切れるようになり、胃腸への負担も軽減されます。
・発音が明瞭になる:特に前歯の隙間や位置異常があると、発音に影響することがありますが、矯正によりクリアな発音に近づきます。
・歯磨きがしやすくなる:歯が重なっている部分が解消されると、歯ブラシが届きやすくなり、虫歯や歯周病の予防にもつながります。
非抜歯矯正は、ただ「歯を並べる」だけでなく、見た目・機能・将来の健康を総合的に考慮した治療です。つじむら歯科医院では、患者様一人ひとりのご希望と状態に合わせて、最適な治療ゴールをご提案しています。
実際に治療された方の症例をご覧ください。
あなたに最適な矯正治療を見つけよう!

矯正治療には、非抜歯・抜歯、マウスピース・ワイヤーなどさまざまな選択肢があります。「どれが自分に合っているのか分からない」と不安に思う方も多いかもしれません。そんな時に重要なのが、正確な診断と丁寧なカウンセリングです。
まずは、気になる症状やご希望(歯を抜きたくない・目立たない装置がいい・治療期間を短くしたいなど)をしっかり伝えることが第一歩です。矯正治療は“見た目”だけではなく“機能”も大切にする医療です。短期的な変化ではなく、10年・20年後の健康と快適さを見据えた治療計画が求められます。
つじむら歯科医院では、精密検査の結果をもとに、非抜歯が可能かどうかを科学的根拠に基づいてご説明し、患者様にとって無理のない、納得のいくプランをご提案しています。初回のカウンセリングでは、不安や疑問を遠慮なくご相談ください。
“歯を抜かない”という選択が可能な場合、そのメリットを最大限活かすためには、患者様自身の理解と協力も欠かせません。私たちと一緒に、理想の笑顔と健康な歯並びを目指して、一歩を踏み出してみませんか?
“歯を抜かない矯正”で、未来の笑顔を守りませんか?
伊勢原市にある再発率0%を追求した見えない非抜歯専門クリニック
『 つじむら歯科医院 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士